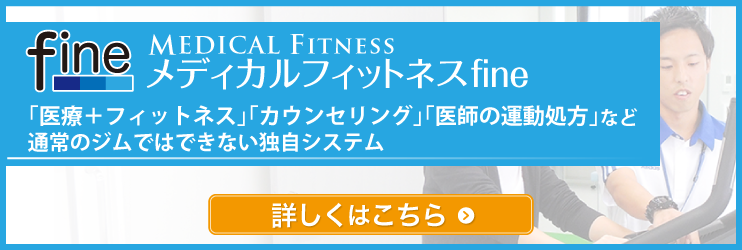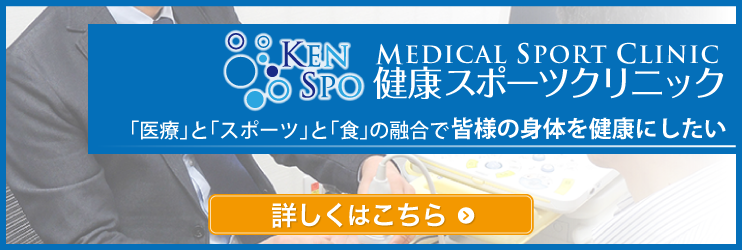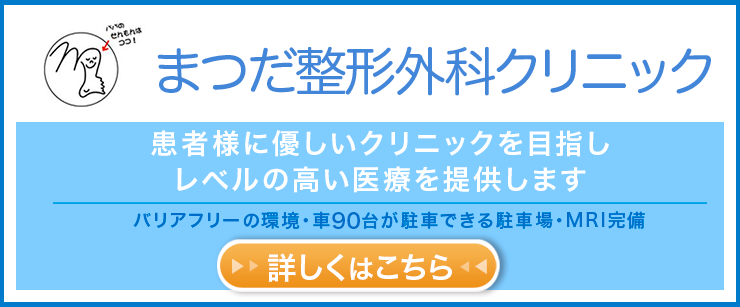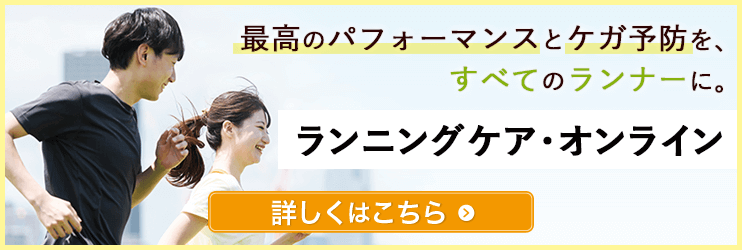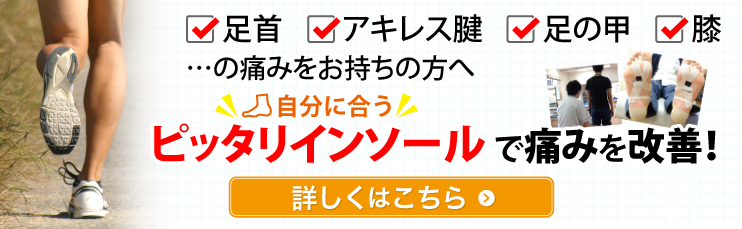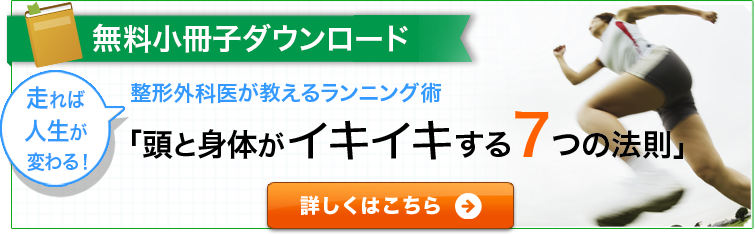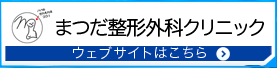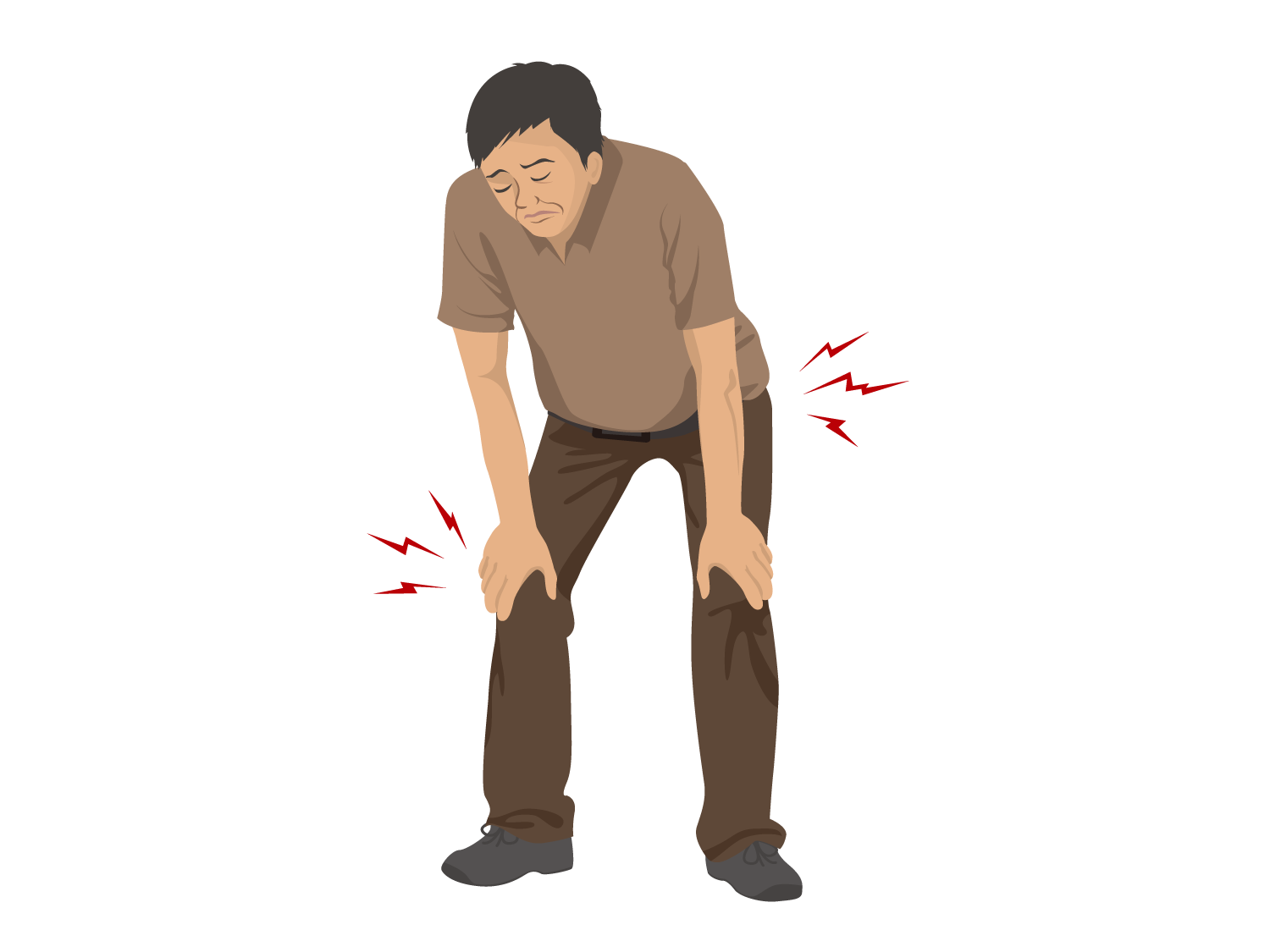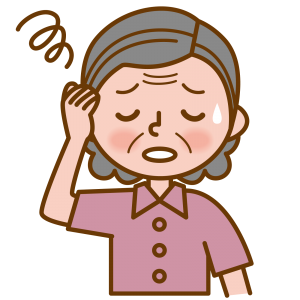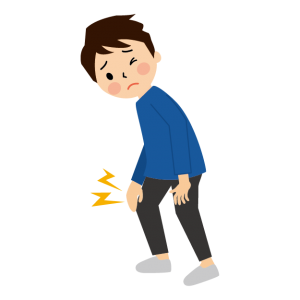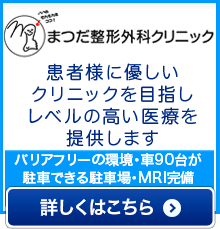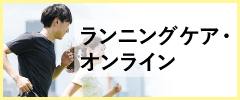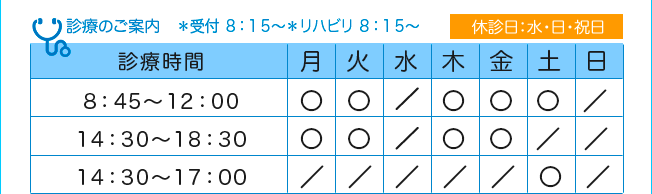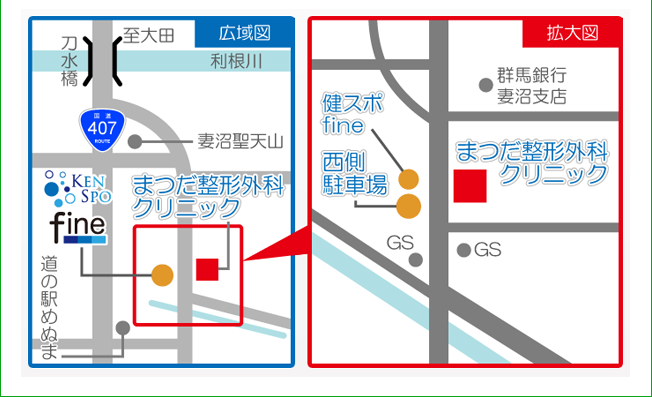足の特徴
<ヒトの足の特徴>
二足直立歩行
まずは、祖先を振り返ってみましょう。
我々の祖先が、二本足直立歩行をはじめたのは、今から数百万年以上も前。
ラマピテクスの時代から、アウストラロピテクスの時代までの間だと推定されているようです。
この二足直立歩行によって、ヒトの足は頭蓋や骨盤とともに最も特殊化した部分になったのです。
足の特徴
ヒトの足は、類人猿と比べ、さまざまな特徴があるのを知っていますか?
1)足が固くて細長く、スマート。
2)物を把持できない。 ← 可動性が制限されているためです。
そして、ここからが最も大きな特徴。
それは…
3)縦方向と横方向に「アーチ構造」を持っている!
まず、自分の足をよ~く見て下さい(^^
縦のアーチとは、足先から踵(かかと)にかけてのアーチです。
土踏まずがはっきりしている方は、このアーチがよくわかると思います。
一方、横のアーチとは、足の内側(おやゆび側)から外側(こゆび側)にかけてのアーチを意味しています。
実はこのアーチがとても大切な働きをしているのです!
アーチ構造の働き
ヒトは基本的に、このアーチ構造を持っています。
ちなみにアーチが形成されていない足を扁平足(へんぺいそく)障害と言います。
これについては、別の機会で詳しくガイドします。
さて、このアーチ構造の働きとは。
●歩行する際に、バネとして働く
●歩行する際に、体重移動を円滑にする
そうです。歩行をスムーズにする役割があるのです。
土踏まずの役割
また、土踏まずの部分も大きな役割があるんです。
それは…
●血管や神経の損傷を防御
なるほど…ですよね(^^
母趾(ぼし)?
さて、足のおやゆびの事を母趾(ぼし)というのを知っていましたか?
英語で「Big toeと」いいます。 ちなみにtoeとは足のゆびのこと。
みなさんの足のゆび、一番大きいのは母趾ですよね。
このように母趾は、よく発達しています。
もちろん、これにも訳があるのです。
何だと思いますか?
それは…
歩く際に、地面を蹴りやすくしているのです。
歩行する際の足の荷重経路
荷重経路?なんだか難しい表現ですみません(汗
歩く時に、どんなふうに足に荷重(体重)がかかるか?という意味ですね。
チョッと歩いて見て下さい。
最初は踵(かかと)をつきますね。
そして、やや足の外側を移動しながら、最後は母趾で終わります。
そう、最後に母趾で地面を蹴って、次の足を踏み出すのです。
普段、こんな事考えて歩いていませんよね。
でも、知ってみるとなかなか面白いと思いませんか(^^
—————————————————————
今週のガイドは如何でしたか?
次回から「扁平足(へんぺいそく)」についてガイドしていきます。
実は、この扁平足。
最近増えているようですね。
ど、どうして(?I?)
次回も お・た・の・し・み・に~
最新の記事